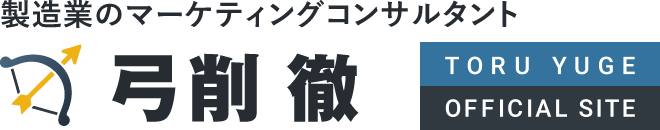製造業がB2C商品を開発するには
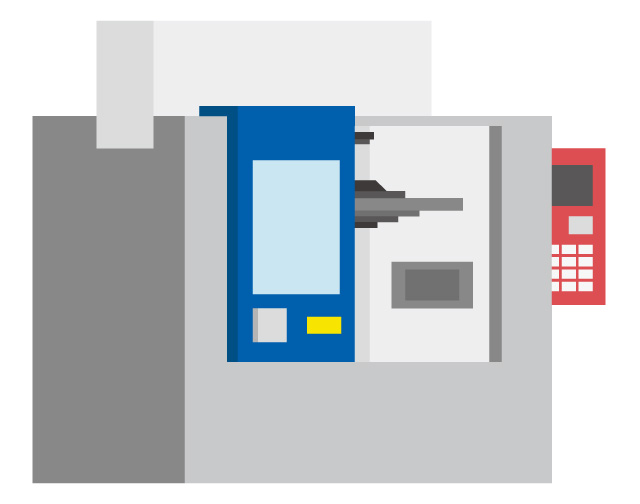
「こういう商品を開発してみたのですが、どうすれば売れるでしょうか?」
何十回となくご質問、ご相談されてきたフレーズです。
悩むまでもなく、最初から売れる商品を開発できればいいわけですが、なかなかそうはいきません。
では「売れる商品」をどうやって見分ければいいのでしょうか。
弓削はそれを「検索される商品かどうか」で峻別できるのではないかと思い至っています。
それはどういうことか?
ご説明していきます。
本業が回っているからこそ新製品開発を
これまでB2C製品のみを製造・生産してきた会社さんにとって、自社ブランドで世に出せる独自商品はひとつの目標です。
景気が好転せず、ケイレツが崩れ、発注元をアテにできないいま、自社のチカラで売上を立てていけるタマ(商品)があるなら、どれほど心強いことでしょう。
そのため、取引先が減少したり、経営者が世代交代したりしたときは、そのチャンスです。
まだ本業が回っているうちなら、次の柱を立てることができますから。
とはいえ、ほとんどの商品開発が失敗に終わっている印象も拭えません。
商品開発をした会社さんには申し訳ないのですが、たとえば電子部品の基板をカットしてストラップにしても売れません。
日頃、主力で扱っている材料のストレッチではあるのと思うのですが、アルミパイプ材を仕入れてレーザー加工をしている工場が、意匠を凝らしたカットをしてロウソク立てを開発しても売れません。
ガラス加工の技術を有する工場が、富士山型のお猪口をつくっても売れません。
まぁ、ふるさと納税の対象商品に選ばれれば少しは売れるかもしれませんが。
(例に出してしまった会社さん、すみません!)
市場規模は小さいのに売れる商品もある
その一方で、段ボールメーカーが猫の爪とぎをつくると売れます。→[キャットタワー]
炊飯をすると糖質をカットできる土鍋は売れます。→[気づかう土鍋]
吸水性が1.5倍あるバスタオルも売れます。→[エアーかおる]
いずれも、切実なニーズがあるから、言ってしまえばそれまでですが、ではバーミキュラはどうでしょう。
無水鍋などは昔からあり、この手の調理器具にもともと切実なニーズがあったとはいえません。
ただ、体験した人だけは、無水調理のおいしさに驚く。
食べた人は、SNSなどに投稿せずにはいられないのです。
同様の匂いがする商品としては、コーヒーの紙フィルターが通さないコーヒー豆の旨味である油脂成分を通す有田焼のフィルター[セラフィルター]も大人気です。

「おいしさ」を求めるニーズは大きな市場性がありますが、こんな事例はどうでしょう。
新潟県・長岡市でのセミナーご参加企業が製造・販売しているのは、爬虫類を飼育するケージの底に敷いてペットが快適な温度を維持できるホットシートでした。
ほとんどの人は興味すら持たないこの製品ですが、生産が追いつかないくらいの受注残を抱えているとのことでした。
ペットを飼っている人にとっては、飼育環境は大問題なのです。
ふつうは大きい市場があれば成功に近いと考える人が多いでしょうが、弓削は「大きな市場と成長市場は避けたほうがいい」と唱えています。
年間1,000億円以上の規模がある市場には大手企業がすでにいるか、あとから参入してきます。
そしてオイシイところを持っていく、あるいはさらに新興国の企業が参入してきて不良品で価格も市場も破壊してしまうのです。
中小企業が安定的に稼ぐにはニッチなほうがいい、新規参入者が魅力を感じないていどの市場規模の方がいいのです。
分岐点は熱のある検索がされるかどうか
とはいえ、以上に挙げた成功商品、ヒット商品に共通して言えることは、熱を込めて探してくれる、つまり検索してくれる人がいるということです。
使用して「よい」と感じた人がSNSに投稿する、「ユニークだ」と考えたメディアが記事にする。
それに触れた人が興味を持ったり、欲しいと思って検索してくれるかどうか。
これにかかっているのだと思います。
上掲の、基板のストラップ、円筒形のロウソク立て、富士山型のお猪口などは、知ったとしても検索したいと思わないし、検索するためのキーワードも思いつきません。
ですので、「この商品企画でいけるか?」と迷ったら、関連キーワードでの検索回数が月間に何回あるかをチェックしてみてください。
日頃、「月間の検索回数が5,000回に満たないニーズはビジネスになりづらい」とお話ししています。
しかし、仮に月間5,000回の検索があり、その検索者の3%が購入に至り、そのうち10%のシェアをあなたの会社が占めると仮定したらどうでしょうか。
5,000回×3%×10%=15回/月間 購入
さらに、検索回数が10,000回であったらどうでしょう。
10,000回×3%×10%=30回/月間 購入
ほぼ毎日、受注があるというわけです。
新規事業の商品としては、夢がもてるのではないでしょうか。
ニッチな商品であれば、シェアは10%どころではないはずです。
商品の品質としては、使用者が感心して自慢したくなるような効果のある商品であればよいわけです。
「検索してもらえる商品かどうか」
このようにシンプルに考えるのも、ひとつの指標となりえるかもしれません。
製造業のマーケティングコンサルタント、弓削 徹(ゆげ とおる)でした。
ものづくりコラムcolumn
- 2025/07/08
- 新刊・重版3刷出来! 深く感謝いたします!
- 2025/06/20
- 機械系エンジニア向け転職エージェントサイトの記事を監修
- 2025/06/11
- 書籍の紹介動画を公開
- 2025/06/08
- 弓削徹の「発信」場所一覧
- 2025/05/21
- 新刊重版・音声配信開始の報告